- ★Google+
- ★Hatena::Bookmark
武蔵野大学薬学研究所(東京都西東京市、山下直美所長)プロテオアナリシス客員研究部門の一番ヶ瀬智子客員講師ならびに今井一洋客員教授のグループによる研究成果が、このたびアメリカの科学雑誌「プロスワン(PLoS ONE)」に掲載された(日本時間9月19日午前9時)。これは、活性酸素の過剰生産による細胞死の仕組みについて、世界で初めてタンパク質レベルで捉えることに成功したことを発表するもので、がん・老化を防ぐ薬の開発が期待される。
薬学研究所プロテオアナリシス客員研究部門は、2003 年に設立した薬学部生命分析化学研究室を前身とし、生命分析化学をさらに拡充する目的で、2012 年 4 月に再編された。同研究部門では、「タンパク質新規解析法(FD-LC-MS/MS法)の確立と展開」をテーマに、生体内中に極微量しか存在しないタンパク質の量を正確に測る方法を研究している。
当該論文は下記を参照。
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0045483
◆発表内容概要
【実証方法】
同グループが開発したタンパク質の網羅的解析法(FD-LC-MS/MS法)を、同大薬学部榎本武美教授らの作成したSODノックアウトニワトリ細胞株(=細胞内に活性酸素が過剰生産されるよう、活性酸素除去酵素である「SOD」を人工的に消失させた細胞株)に適用
↓
多種類のタンパク質の量を正確に測ることができ、ごく微量のタンパク質の変化を捉えることができる
↓
解析した多種類のタンパク質の変化から、増加した活性酸素が細胞を破壊するメカニズムを実証
【実証結果】
●活性酸素が過剰に発生した細胞と通常の細胞中のタンパク質の種類と量を比較し、細胞の破壊に繋がるタンパク質「FKBP52」などが活性酸素過剰細胞に多く存在していることを発見
●一方で、「NDK」などの破壊阻止タンパク質の増加も確認
【まとめ】
活性酸素の過剰発生⇒細胞破壊タンパク質および破壊阻止タンパク質がともに増加している
↓
破壊阻止タンパク質の増加を促す化合物を見つけることで、活性酸素による細胞死(ひいては老化やがんなど活性酸素が原因となる諸症状)を防ぐ薬の開発が期待される
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵野大学 企画部企画・広報課(担当:足立)
TEL: 03-5530-7403
FAX: 03-5530-3818
E-mail: kouhou@musashino-u.ac.jp
URL: http://www.musashino-u.ac.jp/
大学・学校情報 |
|---|
| 大学・学校名 武蔵野大学 |
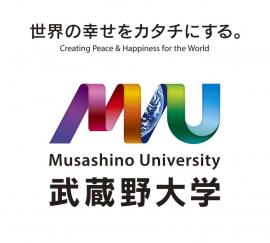
|
| URL https://www.musashino-u.ac.jp/ |
| 住所 〒135-8181 東京都江東区有明三丁目3番3号 |
| 学長(学校長) 小西 聖子 |
 大学探しナビで武蔵野大学の情報を見る
大学探しナビで武蔵野大学の情報を見る