- ★Google+
- ★Hatena::Bookmark
平成21年度文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」【テーマA】大学教育推進プログラムに、聖徳大学短期大学部保育科「自ら考え行動しチーム貢献できる保育者養成―異学年共同コミュニティによる課題解決型学習―」が選定された。
【取組の概要】
聖徳大学短期大学部保育科(以下本学保育科)は、学生一人ひとりの専門的能力・実践力を高め、幼児教育・保育分野で活躍できる人材の輩出、向上心の高い保育者の養成を目標としてきた。しかし近年、学生の学習意欲が低下傾向にあり、知識・理解力不足等が認められる。さらに、考えぬく力・前に踏み出す力の欠如も問題となっている。また、本年4月に実施した学生の自己課題調査では、全学生が自分の学習に対して何らかの課題をもっていることもわかった。
この自己課題を解決するには、主体的な学習意欲を引き出しながら、上記の欠如した力を克服しなければならない。学生の継続的な学習意欲を喚起し、本学保育科の目標実現を確実にするために、学生主体の課題解決型学習(Project-Based Learning)プログラムを考案し、実践する必要がある。
そこで本取組では、1年生と2年生が異学年共同コミュニティを形成し、教員がファシリテーター役となる少人数指導により、学生の主体的な学びを推進する教育プログラムを展開する。コミュニティ形成は、異学年の学生間および学生・教員間の双方向型学習を可能にする。さらに、コミュニティごとに学習テーマ、活動内容、成果発表方法を決定し、実践することにより、幅広い学びの保証をはかる。多様な人間関係の中で、自ら考え、行動していくことは、学びの質とともに、課題発見力・行動力・傾聴力・自己表現力等を向上させる。
具体的には、学生が主体的に見出した自己課題別に、実践学習の場であるコミュニティを編成し、テーマ学習を1年間行う。コミュニティごとのテーマ学習の活動内容、記録等は学生の手に委ねられ、その学習成果を学生フォーラムで発表する。また、全コミュニティの学習活動はデータベース化され、全学生で成果を共有することを可能にしている。
同時に、学生が「プログレスノート」(自分の成長を記録するノート)を作成することで、継続的に自己分析・評価を行い、自己課題解決に結びつける。最終的には、教育・保育現場から強く要請されている課題探求能力と人間関係調整力を有し、チーム貢献できる人材の育成を目指す(概念図参照)。
本取組は、学生の自己評価、学生間評価、ファシリテーターとしての教員の評価、学生フォーラムにおける外部評価など、さまざまな角度、指標により多面的な評価を実施し、PDCAサイクルで改善、発展を続けることで、学生の学士力と取組の実効性を高めていく。近い将来、取組の成果を地域へ発信していくことや、本取組で目標を達成した卒業生による支援体制を構築することで、幼児教育・保育の質向上に一層貢献できるものと考える。
※平成21年度 文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」【テーマA】大学教育推進プログラム 申請・選定状況:私立短期大学からの申請数は63件、選定数はわずか8件。
※なお、聖徳大学短期大学部 保育科の取り組みは、本年7月、平成21年度 文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」【テーマB】学生支援推進プログラムにも1件採択されている。
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学・聖徳大学短期大学部
知財戦略課
TEL:047-365-1111(大代)
〒271-8555千葉県松戸市岩瀬550
http://www.seitoku.jp/
大学・学校情報 |
|---|
| 大学・学校名 聖徳大学 |
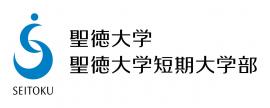
|
| URL https://www.seitoku-u.ac.jp/ |
| 住所 〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地 |
| 聖徳大学は6学部(教育学部、心理・福祉学部、文学部、人間栄養学部、看護学部、音楽学部)8学科を擁し、聖徳大学短期大学部は3学科(保育科第一部、保育科第二部、総合文化学科)と専攻科を擁する女性総合大学です(大学院は共学)。建学の精神「和」に基づいた人間教育を礎とし、豊かな人間性と自立性を備えた品格ある女性の育成を目指しています。 |
| 学長(学校長) 川並 弘純 |
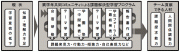
 大学探しナビで聖徳大学の情報を見る
大学探しナビで聖徳大学の情報を見る